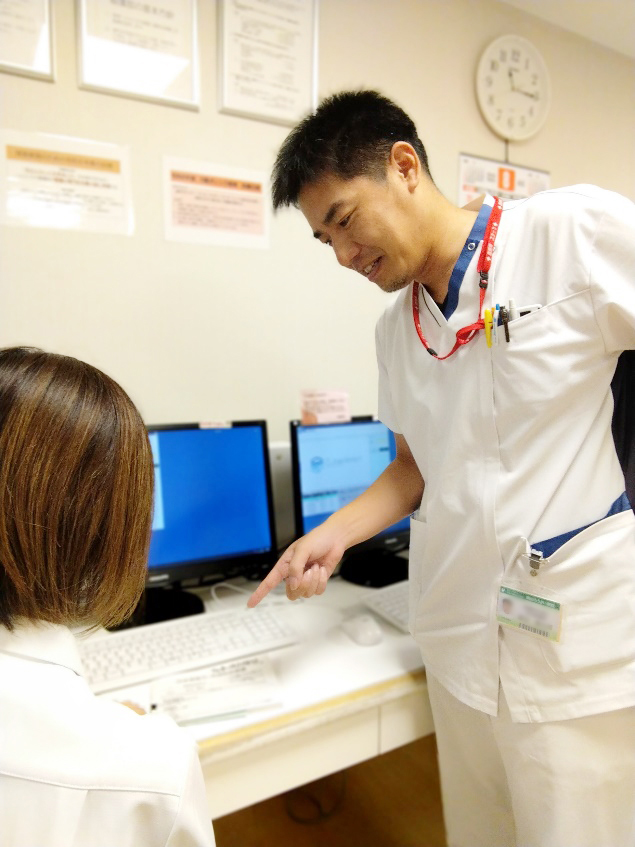高度な治療とモニタリング
回復につながるサインを見過ごさない!
ICUは呼吸循環代謝を障害され、集中的に全身管理が必要な患者さんを担当しています。24時間モニターから繰り出される数値から、患者さんが最適な状態であるのか判断し、タイムリーな治療・看護を展開しています。
患者さんが自ら症状の訴えができないことも多いため、患者さんが少しでも安楽な状態となるよう細やかなケアに心がけています。また、現在患者さんがもつ機能をできるだけ維持できるよう、早期にリハビリテーションが介入し、点滴ではなく消化管を使用した栄養の取得にむけ栄養サポートチームが介入しています。他職種チームが専門的な視点を持ち、最前線で患者さんの生きる力を支えています。